
日本の消費税は高い?低い?世界の消費税率ランキングや軽減税率の仕組み、日本と海外の違いを詳しく解説します。増税のメリット・デメリットも理解できる必見の内容です!
目次
日本より消費税が高い国はあるのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。消費税が高い国や、高い税金を払うメリット・デメリットについて解説します。判断を迷いやすい軽減税率に関しても、併せて覚えておきましょう。
そもそも消費税とは

消費税の基礎知識をおさらいした上で、消費税が高い国について詳しく解説します。税率20%以上の国はEUに集中していることを知っておきましょう。
■消費一般に課される税金
消費税とは、商品やサービスなど消費するもの全般に対し、公平に課される税金です。消費者が支払った消費税は、納税義務者を通して国や地方自治体に支払われます。
医療費や授業料など特定のものを除き、ほとんど全ての物品やサービス提供に消費税が課税されます。間接税の一種であり、消費者が消費税を支払うのに特別な事務手続きなどは必要ありません。
消費税は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を控除し、差額を納付する仕組みとなっています。生産や流通の段階で二重課税が発生するのを防ぐ仕組みです。
■消費税の高い国ランキング
外務省が公表している最新データから、2023年4月時点での税率の高い国が分かります。最も税率の高い国はハンガリーで、税率は27%です。2位以降の国は以下。
- クロアチア:25%
- スウェーデン:25%
- デンマーク:25%
- ノルウェー:25%
- アイスランド:24%
- ギリシャ:24%
- フィンランド:24%
- アイルランド:23%
- ポーランド:23%
- ポルトガル:23%
そして、⽇本の標準税率は、OECD加盟国とEU、ASEAN+3(+台湾)の合計51ヵ国中、42位で下から7番⽬です。世界的にみても低い税率であることがわかります。
参考:
■税率20%以上の国はヨーロッパに集中
2021年現在の日本では、標準税率が10%、軽減税率は8%と定められています。日常生活の消費活動において、ほぼ全ての消費に税金がかかるため、税率が高いと感じている人も多いでしょう。
しかし、世界には日本より消費税率の高い国が数多く存在します。税率が20%を超えている国も多く、消費税が高い国はヨーロッパに集中していることが特徴です。
■EUの税率が高い理由
全てのEU加盟国は、EUの基本法令である『VAT指令』により、標準税率を原則15%以上とするよう義務づけられています。VATとは『付加価値税』のことであり、日本の消費税に該当する間接税です。
ヨーロッパ各国の税率が軒並み高い理由は、全てのEU加盟国で共通税制のVATを導入していることが背景にあります。ただし、日本と同様に軽減税率が認められており、食品や医薬品の税率はどの国もおおむね低めです。
中には、食品や医薬品の税率を0%にしている国もあるなど、同じEU加盟国でも政策に大きな差があります。本質的な単一市場を目指すEUにとって、国による課税ルールの大きな違いが問題視されることもあります。
付加価値税(VAT)は、消費税と同様に間接税の一種です。製造や流通の過程で課税され、最終的に消費者が負担します。付加価値とはどのようなものを指すのでしょうか?付...
■消費税の低い国の特徴とは
消費税が低い国には、主に他の税収が豊富であることや、政府が異なる税制度を採用しているという特徴があります。例えば、所得税や法人税が高めに設定されている国では、消費税率を低く抑えることができます。
また、資源が豊富な国は、天然資源の輸出などによって得た収入で税収を補っているため、消費税が低い場合があります。さらに、観光業が重要な収入源となっている国では、観光客の消費を促進するために消費税を低く設定することもあります。
使い道は何?高い消費税を払うメリットとデメリット
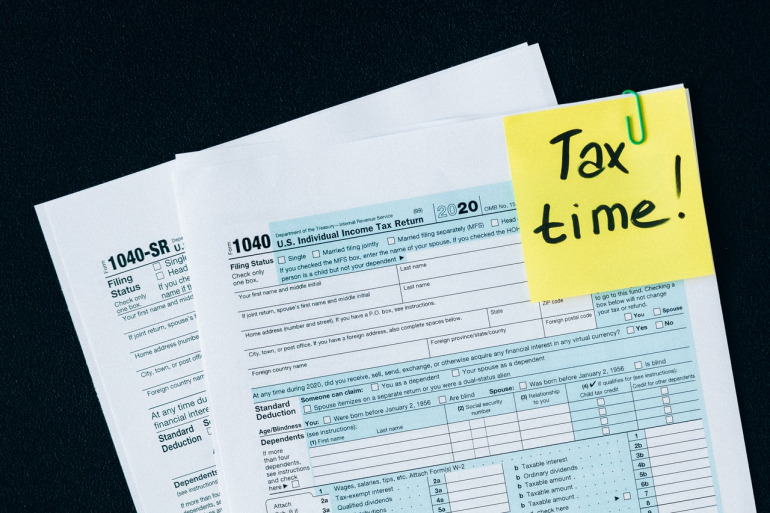
(出典) pexels.com
消費税率を高く設定することには、メリットとデメリットがあります。それぞれについて詳しく解説します。
■社会保障・社会福祉の安定が最大のメリット
日本で消費税が8%から10%に増税された最大の目的は、社会福祉のさらなる安定です。増税により徴収された税金は、『待機児童の解消』『教育・保育の無償化』『介護職員の処遇改善』『高齢者の介護保険料軽減』などのために役立てられることとなっています。
社会保障には多額の財源を必要としますが、高齢化により財源がさらに膨れ上がっている上、少子化の影響で財源の確保も厳しくなっているのが現状です。
そのため、景気などにより税収が不安定になりやすい所得税や法人税ではなく、安定した税収を見込める消費税が増税の対象に選ばれています。地方消費税の増税により、自治体の税収を安定させられる点もメリットです。
2022年現在、日本の消費税は10%(軽減税率8%)です。段階的に上がってきた税率を見て、「消費税は何に使われているんだろう?」と疑問に思う人も多いでしょう。消...
仕事をして給料や報酬を得る際に発生する『所得税』は、日本以外の国にも存在します。日本の所得税は、世界と比べて高額なのでしょうか?所得税における日本と外国の共通点...
■家計にかかる負担がデメリット
消費増税による大きなデメリットは、家計への負担が増すことです。消費税率が5%から8%に引き上げられた際も、個人消費は落ち込む傾向が見られました。
家計にかかる負担が増え、世間で買い控えの動きが大きくなると、企業の売上が減少します。景気が悪化し、法人税の税収が少なくなることにもなりかねません。
また、個人消費が落ち込むことで、消費税の税収自体も減る可能性があります。税収増を見込んで税率を引き上げたにもかかわらず、増税で購買意欲が減退し、税収が減るリスクがあるのです。
知っておきたい軽減税率の基礎知識

(出典) photo-ac.com
軽減税率とは、特定のものを消費する場合に限り適用される、標準税率より低い税率です。EUの軽減税率と、日本で軽減税率の対象となるものについて解説します。
■EUでの軽減税率
消費税が軒並み20%を超えているEU各国では、多くの商品を軽減税率の対象としています。商品によっては、税率を0%としている国もあるほどです。
例えば、税率20%のイギリスでは、食料品・医療用品・書籍・子ども用衣類などに消費税がかかりません。税率が25%のスウェーデンでも、食料品や宿泊費は12%、書籍やイベントチケットは6%などとなっています。
テイクアウトの種類により税率に差があるのも特徴です。イギリスは外食時と温かいテイクアウトは税率20%がかかりますが、冷たいテイクアウトは非課税です。
■日本ではどんなものが対象なの?
日本で軽減税率8%の対象となるのは、『酒類・外食を除く飲食料品』と『定期購読で購入する新聞』です。
食料品・飲料・テイクアウト・宅配ピザ・持ち帰り弁当などが、『酒類・外食を除く飲食料品』に該当します。イートインは外食扱いとなり、軽減税率は適用されません。
標準税率10%が課税される主なものは、水道水・アルコール・日用品・店内飲食・レストラン飲食です。ケータリングや出張料理も、軽減税率の対象外となります。
ティーカップと紅茶のセットなど、食品とそれ以外のものが一体となっている商品は、『税抜き1万円以下』かつ『食品が全体の2/3以上』なら税率は8%です。
イートインとテイクアウトで異なる消費税率、もし嘘の申告をしたら罰則は発生する?
食べ物や飲み物を買うとき、イートインとテイクアウトで消費税率が変わります。それぞれの税率とともにイートインの判断基準や条件を紹介します。イートインを利用するとき...
構成/編集部















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE

















