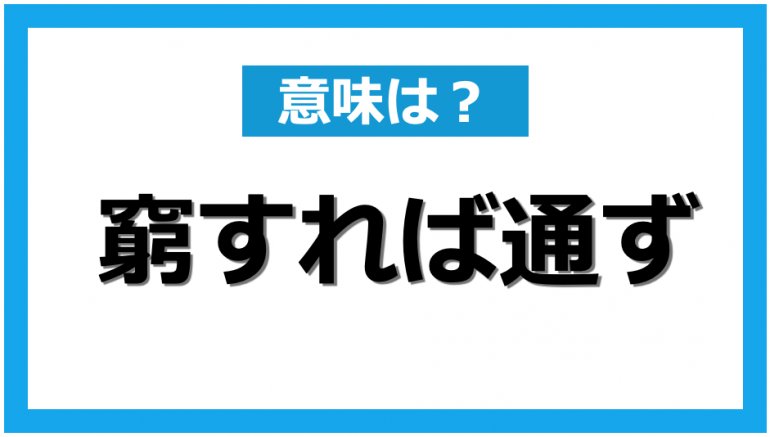
日本で使われることわざの一つに「窮すれば通ず」がある。簡単に言うと「窮地に陥ったときに、思いがけない道が通じるものだ」という意味だ。最近ではあまり耳にする機会もなくなったが、意味を覚えておいて損はない。
そこで、本記事ではこの「窮すれば通ず」について、正しい意味や使い方を紹介する。ビジネスシーンでも活用できる言葉なので、ぜひ使いこなしてほしい。
「窮すれば通ず」とは
このことわざの起源は、中国の古典。長い歴史を持ったことわざの一つだ。はじめに、「窮すれば通ず」の正しい意味や語源をチェックしていこう。
読み方と意味
読み方は、「窮(きゅう)すれば通(つう)ず」、もしくは「窮(きゅう)しては通(つう)ず」とも言われる。「通ず」は、「通じる」や「通ずる」とされることもあるが、一般的には「通ず」が広く使われる。
「どうにもならないような追い詰められた状況に陥ると、思いのほか道が開けて活路を見いだせるものであり、八方塞がりのように思える状況でも解決する方法は見つかること」を表現したことわざだ。また、自身の工夫がなくとも「運命的に、奇跡的に」道が開けた場合にもこのことわざが使われる。
語源
「窮すれば通ず」は、中国の古典「易経」の一文が語源と言われる。「易経」とは、およそ3,000年前に発展した「易」という学問を経典としてまとめたもの。後に儒教の経典「五経」に組み入れられたとされる占い、哲学の書。森羅万象の変化の法則を説き、古来政治における重要な意思決定の場面で今後の行方を占うために用いられていた。
その中にある「窮すれば即ち変ず、変ずれば即ち通ず、通ずれば即ち久し」の一文が、このことわざの由来だ。この文は「行き詰まったときは何か変わらざるを得なくなる、何かが変わると新しい道が開ける、その繰り返しをしていくことで長く道を続かせることができること」を意味している。
「窮すれば通ず」の類義語、対義語

次に、「窮すれば通ず」の類義語や対義語を紹介する。それぞれを比較するとまた違った角度から知識が深まるはず。
類義語とその違い
「窮すれば通ず」の類義語の一つが、「必要は発明の母」。これは英語のことわざ「Necessity is the mother of invention」を訳したもので、「必要に迫られることでさまざまな工夫を凝らし、新たな発明を生むことができる。必要とは発明を生み出す母のようなものだ」という意味で、現状を変えるために工夫や改善を続け、それにより新しいものを生み出すという点で、「窮すれば通ず」と近い意味を持つ。
ただし、「窮すれば通ず」は危機的な状況を前提としているが、「必要は発明の母」は追い込まれた事態を表しているわけではない点に違いがある。
対義語
「窮すれば濫す(きゅうすればらんす)」が「窮すれば通ず」の対義語にあたる。「人は追い込まれた状況に陥ると物事の良し悪しの区別が付かなくなり、悪いことにも手を染めてしまうこと」を意味し、中国の思想家、孔子とその弟子の言葉を記した『論語』の一部が基になっている。
弟子を引き連れた孔子一行が、国家間の争いの影響により数日間飲まず食わずの状況が続いた際、過酷な状況の中でも孔子が平静と変わらずにいたことから、弟子が「君子も窮することがあるのでしょうか?」と孔子に質問し、これに対し孔子が「君子は窮しても道をはずすことはない。『小人窮すれば斯(ここ)に濫す』」と答えた。「小人(しょうじん)」とは「徳や品性を欠いた卑しい者」を表し、そうした者は追いつめられると自暴自棄になる、と説いた一文だ。
窮すれば通ずの使い方と具体例
最後に「窮すれば通ず」を生活の中で活用できるシーンや、実際の使用例を紹介したい。正しい意味を把握したら、適したシーンで使ってみるとスマートかもしれない。
使用シーンと注意点
先述した通り、窮すれば通ずは「追い込まれた状況」を前提としている。物事が行き詰まりどうにもならないときに励ましの言葉として声を掛けたり、厳しい状況をなんとか乗りこえたときにねぎらったりする際に使いやすい言葉だ。
使用する際の注意点として、「窮すれば通ず」は一文が一つの表現になったことわざのため、語末の「通ず」を動詞として活用させることはできないことを覚えておこう。例えば、「一時はどうなるかと思ったが、窮すれば通じた」などの使い方は誤りだ。
「窮すれば通ず」を使った例文
・「窮すれば通ずともいうのだから、諦めずに続けてみよう」
・「とても厳しい納期のプロジェクトだったが、窮すれば通ず、チームメンバーの素晴らしい連携により成功を収めることができた」
・「倒産の危機に直面したが、それを機に経営戦略の大幅な改革を行ったことで、さらなる成長ができた。まさに窮すれば通ずである」
・「成績が伸び悩みスランプに陥っていたが、窮すれば通ず、1日の行動計画の改善をしたら大きな結果を出すことができた」
文/oki















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE













