
犬が死んだ朝
往診に来た獣医は「今夜中だと思います」と言って帰った。
老人と死にかけた小さな犬だけが取り残された。犬は朝日を見ることなく、亡くなるらしい。今はただ、横たわった体を優しくなでている。
亡くなった妻はこの犬を溺愛し、心配していた。きちんと世話をしているのか、夫の私のことよりも気にしていた。
見舞いに行くと「あの子はどうしてるの?」と聞かれるので、安心させたくて、たくさんの写真を撮影して病院に持って行った。
写真を枕元に置いておくと、若い看護師が「可愛いわんちゃんですね」と声をかけてくれる。
「ペットショップで一目ぼれしたのよ」と妻は嬉しそうだった。真っ黒で大きな瞳の、賢い犬だった。うるさく吠えることもなく、散歩の犬仲間も多く、誰からも可愛がられた。
病院のベッドで「あの子に会いたい。ひとめで良いから会いたい」と泣かれたので、ワゴン車を借りてきて、病院の駐車場でこっそり引き合わせた。
興奮した犬が吠える声をはじめて聞いた。妻は犬の匂いを思い切り吸い込んで、思い残すことは何もないと呟いた。
老人の一人暮らしを心配して、いろいろな人が勝手に忠告してきたが、妻が亡くなっても犬との二人暮らしを変える気はなかった。散歩や食餌など、日常生活は犬が中心となり、妻の穴を埋めて余りある、とてつもなく大きな存在になっていった。
「あなたねえ、ヨーキーって犬は、イギリス貴族を夢中にさせた犬なのよ」と妻がよく自慢していた通り、人の気持ちを読み取るのが得意な犬だった。人を見分ける判断力に優れていて、犬好きで可愛がってくれそうな人を見つけるのが、得意だった。
散歩には全身全霊をかけて一生懸命な一方で、普段は家の中で一番、快適な場所で昼寝をする。オンとオフの切り替えも素晴らしかった。
何より膝の上に乗ってくるタイミングが絶妙だった。妻が亡くなってしばらくしたある日、夕飯の食材を買いに商店街の八百屋へ行った。
混雑している店で、おやじがおかみさんを怒鳴っている声が耳に入った。普段なら聞き流すのに、なぜかその時は、おやじに腹が立って、いてもたってもいられない気分になってしまった。
カゴに入れた大根やネギをそのまま店に置いて、無我夢中で家に帰った。水を飲んでソファーに座り、おおきな息をついたら、犬がぴょんと膝に乗ってきた。どくどく脈打っていた身体が楽になり、血圧が下がった。
犬の背中を撫でていると、振り返って小さな舌で、優しく舐めてくれる。なごんでいるうちに、自分があのおやじに激しく嫉妬していたのに気が付いた。
八百屋の主人がおかみさんを怒鳴り、おかみさんも負けずに言い返す。自分たちは人前で、あんなにみっともないケンカをしたことがない。
いつも穏やかだったし、妻はおかみさんよりもずっと上品で美しかった。でも、八百屋の夫婦は今、二人でいるのだ。
ヨークシャー・テリアは膝の上でもっと撫でてくれとせがみ、私はずいぶん長い間、犬を抱いて撫でていた。もう大丈夫、と思えるまで付き合ってくれた。
一番の思い出はノーリードで草原を走り回ったことだ。妻の実家が広い牧草地をもっていて、そこへ連れて行った。当時はまだ妻も元気で、里帰りが嬉しそうだった。
広い牧草地で犬を放すと、振り返りながら、かなり遠くまで行ってしまい、心配した妻が大声で名前を呼んだ。すぐに振り返った犬は、そこから全速力で戻ってきた。自分が帰る場所は、あなた達のところだ、と。
眠っているように横たわった犬を見ていると、楽しかった犬との思い出があとからあとから溢れてくる。最後の時、看護師は「耳は最後まで聞こえますから、声を掛けてあげてください」と教えてくれた。
あの時、何と声を掛けたのか、今は思い出せない。犬には「ありがとう」以外、何と言ったらいいのだろう。
死にゆく犬へ、かけるべき言葉が書いてある本はないか。
ふらふら立ち上がって、暗い書棚に本を探した。昔の詩集を引っ張り出して開いてみる。そこにあった言葉は、犬からのメッセージだった。
「さよなら」とわれ叫ばん
いざわれは汝を離れて
とび行かん未見の空のあなたに。
(村山槐多「過ぎし日に」より)
文/柿川鮎子(PETomorrow編集部)
構成/inox.
え、知らないの?笑って泣ける犬猫マガジン「PETomorrow」
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE














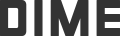 最新号
最新号






