
5月病はめずらしいものではなく、年齢やキャリアを問わず発症する可能性があります。かからないように対策するのはもちろん、万が一のときの対処法も頭に入れておきましょう。症状によっては自力で解決しようとせず、専門家への相談が必要です。
5月病とは
5月病は誰もが発症する可能性があるといっても過言ではありません。5月病というその名の通り、「充実した連休を過ごしたから、単に仕事に復帰しづらいだけだ」と勘違いしている人もいますが、真面目な人ほどかかりやすいともいわれています。
症状によっては、仕事や日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。
特に理由なく心身の状態が優れない状態
5月病は医学的な病名ではなく、あくまでも通称です。おもに5月のゴールデンウィークが明けたころに、心身に不調が現れることを指します。
症状が人によって異なるのも、大きな特徴です。気分が落ち込んだり集中力が低下したりして、今まで簡単にできていたことが突然できなくなる人もいます。夢中になっていた趣味でさえ、興味が持てなくなるケースも少なくありません。
精神的な不調だけでなく、疲れやすい・倦怠感・不眠・めまい・動悸・食欲不振・胃痛など体のトラブルが現れることもあります。
環境変化からしばらくして発症することが多い
5月病の原因として考えられるのは、環境の変化です。4月に新生活をスタートした人が、5月ごろから心身の不調を覚えることがあります。かつては新入社員に多く見られる現象でしたが、転職や人事異動などで中高年がかかるケースもめずらしくありません。
新しい環境で成果を出そうとやる気に満ちあふれていた人が、しばらくしてから急に無気力状態に陥るのも5月病といえます。
5月病が発症するのは、5月に限ったことではありません。研修期間を終えて実務をこなすようになる6月やお盆休みが終わった8月に発症するケースもあります。
疲労やストレスの蓄積が原因となる
環境の変化が大きければ大きいほど、疲労やストレスによる負担も増えます。疲労もストレスも、心身のトラブルを招く原因です。特にストレスは知らず知らずのうちにため込みやすく、ある日突然限界を迎えてしまう人もいるでしょう。
実際に5月病はストレスを抱えこみがちな人が発症しやすいとされています。ストレスを蓄積しやすい性格にも傾向があり「几帳面」「我慢強い」「完璧主義」「責任感が強い」といった、いわゆる『真面目な人』ほど注意が必要です。
真面目な人は周囲からの評価が高い一方、期待に応えようと無理をする一面があります。人に弱みを見せるのも苦手で、悩みも1人で抱えこみがちです。
5月病にならないための対策は?

5月病は日々の生活習慣によってある程度は防ぐことができます。仕事が忙しくて生活が荒れている人は、できることから少しずつ改善を図ってみましょう。ストレスや悩みが深刻になる前に、周りの人に頼る勇気も必要です。
参考:「五月病」に対策するための5つの方法 今日から始めるストレス対処法 | ニュース | 保健指導リソースガイド
規則正しい睡眠や食事を心がける
疲れをためないように、規則正しい睡眠習慣を心がけたいところです。睡眠は日々の疲労回復に欠かせません。限られた時間で疲れをとるためには、睡眠の質を高めることも大切です。
なかには帰宅時間が遅く、食事もお風呂も寝る直前に済ませる人もいるでしょう。しかし、食事は寝る2時間前、お風呂は1時間前に済ませるのが理想的とする説もあります。寝る前のテレビやパソコン、スマホも控えましょう。
栄養バランスも重要です。食事は1品で済ませるのではなく主食・副菜・主菜を組み合わせることで、栄養の偏りを防げます。
ストレスをためない
ストレスをためないようにするには、意識的に発散する必要があります。ストレスを解消する方法はいくつかありますが、手軽さや効率を重視したいなら運動がおすすめです。
運動をすることで、ストレスなど精神的な疲労を軽減する効果が期待できます。適度な運動を心がけることは気分転換になります。体を動かしている間は仕事などの悩みも忘れられ、気持ちを切り替えることにもつながります。
軽いウォーキングやストレッチでもいいので習慣化して、ストレスをこまめに解消しましょう。
同僚や家族とコミュニケーションを取る
周りの人に悩みを打ち明けるのが苦手な人もいるでしょう。責任感が強い人は「迷惑をかけるわけにはいかない」と思い、1人で抱えこみがちです。プライドが邪魔をして、他人に助けを求められない人もいます。
悩みを相談することは、迷惑なことでも恥ずかしいことでもありません。悩みを言葉にすることで、現状を打開する方法がおのずと見えてくることもあります。
自分では考えつかない意見をもらって、解決の糸口が見えることもあるでしょう。解決に直接結びつかなくても、話を聴いてもらうだけで気持ちが楽になることも少なくありません。
5月病になってしまったらどうする?

5月病になった自分を責めても、つらくなる一方です。私生活では気持ちが前向きになるように、有意義な時間を過ごしましょう。仕事の悩みも1人で解決しようとせず、信頼のおける上司や同僚に相談するのも手です。
引きこもるより、楽しい生活を心がける
5月病になると悩みや不安に心が支配されて、気分が晴れない日が続きます。何もする気が起きず、部屋に引きこもりがちになる人もいるでしょう。
引きこもっていれば体の疲れは癒えるかもしれませんが、気分はどんどん沈んでいってしまいます。落ち込んでいるときこそ、自ら行動に移すことが肝心です。積極的に趣味や好きなことをして、気分を切り替えましょう。
ただし、どんなに食べることやアルコールが好きでも、暴飲暴食は禁物です。体に大きな負担がかかって、疲れやすくなってしまいます。
健康に気を付けながら、楽しく過ごすことを心がけてみましょう。
仕事量を調整する
新社会人でなくても、社会人である以上は新しい挑戦の連続です。
転職したり会社を立ち上げたりするなどして、大きな変化が訪れることもあります。職場はそのままでも、部署や上司が変わって環境がガラリと変わるのもよくある話です。
仕事が原因で5月病になった場合、仕事量を見直すことで解決することもあります。自分に権限がない場合は、上司に相談してもよいでしょう。単純に仕事量を減らしてもらえるだけでなく、悩みを打ち明けることで労働環境の改善も期待できます。
それでも5月病が改善しない!どうすればいい?

5月病という病名はなくても、心の病に発展する可能性もゼロではありません。忙しいからといって不調を放置していると、さらに悪化するおそれもあります。自分だけで解決しようとせず、専門家に相談しましょう。
うつ病に移行してしまう場合もある
5月病の症状が軽い場合は、生活習慣などを見直すことで改善される可能性もあります。しかし、5月病は『適応障害』であるケースも多く、ストレスの強さによっては、うつ病と診断されることも考えられます。
「どうせ5月病だから大丈夫」と軽く見ず、心のSOSをキャッチしたら少しでも早く改善を図ることが求められます。
専門家に相談してみよう
5月病は一過性のものであり、心身の不調も「環境に適応すれば治る」と考えられてきました。ところが近年では長引くケースも認められ、自力では改善されないこともあります。
イライラ・思考力の低下・抑うつ状態・食欲不振・睡眠障害などの不調が続くようであれば、我慢をせず、心療内科や精神科などの医療機関に足を運んで医師や専門家に相談することが大切です。
構成/編集部
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










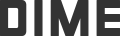 最新号
最新号






