
スマホユーザーであれば、月々の利用料金をなんとか抑えたいという人は少なくないでしょう。通信料金の節約に関連してよく目にするのが『MVNO』という言葉です。MVNOとは一体何なのか、その内容をはじめ、利点・欠点などを掘り下げます。
そもそもMVNOって?
「スマホ関連の費用をどうしたら安く済ませられるだろう?」と考えてネットで検索していて『MVNO』に行き着くケースは少なくありません。
ですが、MVNOに切り替えてみようと思っても、「安くはなりそうだが仕組みがよく分からない」「手続きが面倒そう」といった理由で敬遠してしまう場合もあるでしょう。
とはいえ「MVNOを知った上で使わない」のと「MVNOがよく分からないから使わない」というのでは大きな違いがあります。まずはMVNOの概要を知ることで、自分のスタイルに合うか合わないか判断してみてください。
格安SIMを提供する事業者
MVNOとは『仮想移動体通信事業者』のことを指します。Mobile Virtual Network Operatorの頭文字を取った略語です。
仮想といわれると難しく聞こえますが、『格安SIM』というよく目にするサービスがMVNOに該当します。
大手キャリアと比較して通信量が安いことが特徴で、魅力でもあります。かつてはサブ機や一時的に使用するスマホ用などにMVNOを選択するケースもありましたが、現在ではメインのスマホをMVNOにしている人も珍しくなくなってきました。
MVNOと大手キャリアの違いとは

MVNOはスマホに掛かるコストを安くするカギを握るといっても過言ではありません。MVNOの安さの秘密と大手キャリアとの違いを掘り下げていきましょう。
通信設備を持たない
メジャーなキャリアとMVNOが明確に区別される点は、自社で通信設備を保有しているか否かという点にあります。MVNOは自前の無線通信回線設備は持っていません。
NTTドコモ、ソフトバンク、auといった大手キャリア3社は、『基地局』『交換器』などの通信設備を持っています。その上で、スマホを含む携帯電話サービスを提供しています。こちらは『移動体通信事業者』、Mobile Network OperatorのイニシャルをとってMNOと呼ばれます。
これに対して、通信設備を持たずに携帯通信サービスを提供していることを『Virtual(仮想)』と表現し、Mobile Virtual Network Operator、略してMVNOと呼ぶのです。
低コストで運営
携帯電話サービスを各ユーザーのもとに提供するためには、全国にアンテナや基地局を設置して通信網を整備する必要があり、莫大な費用がかかります。
初期投資のみならず、維持費にも大きなコストが必要です。それらのコストは、通信料が高くなることに影響します。
一方のMVNOは、それらの設備を保有しておらず、大手キャリアの設備をレンタルすることで通信サービスを提供しています。それゆえ、3大キャリアと比べて初期費用やランニングコストの負担が軽くなり、低価格でのサービス提供につながるのです。
MVNOのメリット

MVNOの概要や、運営上の特徴について見てきました。次に、MVNOを利用した際のメリットについて、具体的に見ていきましょう。
料金を抑えられる
ユーザーにとって、MVNOの最も魅力的なメリットが『利用料金を抑えられる』ことでしょう。実際に、コスト軽減を理由にMVNOを使っている人がたくさんいます。
価格面だけでとらえれば、その差は歴然です。大手通信キャリアで月に5000円以上かかるようなプランでも、月に1000円ほどの基本料金で済む場合もあります。
先述のように、通信設備を持たないことで運営コストが大幅に低減されていることが、利用料にも反映されているのです。
古い端末を活用するのに便利
MVNOは、SIMカードのみの契約が可能です。このことと価格の安さから、古い端末を活用するためにMVNOを利用するという使い方ができます。
機種変更をして、もう使用しなくなったスマホやタブレット、モバイルルーターなどがあるとします。それらにMVNOのSIMカードを差すことで再利用し、データ通信専用にしたり、他の家族用にしたりできるのです。
プランに選択肢がある
大手通信キャリアのプランを見てみると、『通話かけ放題+データ通信量』で構成されていることに気付くでしょう。この組み合わせが大手3社のベーシックなプランです。
他方、MVNOでは数多くの選択肢から自分に合ったものをチョイスできます。『通話+データ通信量』『データ通信だけ』など、ニーズに合わせたプランニングが可能となっています。
さまざまなサービスがオールインワンで受けられる大手と比べた場合、MVNOは目的や頻度に応じて料金プランを柔軟に選択できるのは大きなメリットといえるでしょう。
MVNOのデメリット

何事もメリットがあればデメリットも見られるものです。MVNOを利用する際のデメリットについて理解しておきましょう。
設定が面倒
MVNOは、いわゆるショップを持っていないことが多いです。申し込みは、パソコンやスマホなどからインターネットを通して行うのが一般的です。
この時、申し込みからSIMカードの受け取り、初期設定でのAPN(アクセスポイント名)の変更、そして開通手続きに至るまで、すべて自分で行わなければなりません。
慣れている人にとってはさほど難しくはない作業ですが、不慣れだと少しわずらわしく面倒なものです。たいていの人はそう何度も経験することではないので、設定に戸惑うこともあるでしょう。
災害時に不安?通信速度が遅い
通信速度については、若干不安も感じられます。大手通信キャリアと比べてしまうと、時間帯によってはMVNOの通信速度が遅い傾向が見られるのです。
メールを確認したり、文字中心のWebサイトを眺めたりする程度であれば問題ないでしょう。容量の多い音楽や動画などの視聴やダウンロードを行うには注意が必要です。
災害時においては、MVNOにやや不安も感じられます。災害時の音声通話に規制がかかる可能性があるのはMNOも同様ですが、MVNOではキャリアが提供する災害用伝言版は使用できません。
とはいえNTT東日本が提供している災害用伝言板(web171)なら、MVNOユーザーでも使用できます。代わりの方法を用意することで、災害時に備えることが可能です。
キャリアメールの使用不可
大手キャリアを利用してきた人の中には、キャリアメールを使っている人も多いでしょう。長年使ってきたメールアドレスを変えることに抵抗があるという人も少なくありません。
MVNOにすると、キャリアメールは利用できなくなります。大手キャリアの中には、その会社の回線の契約を継続することで利用可能な場合もありますが、基本的にはキャリアメールの使用はできなくなると考えておきましょう。
MVNOへ乗り換える方法

費用面の安さが大きな魅力のMVNOですが、乗り換えるにはどのような方法を取る必要があるのでしょうか。
MNP予約番号を取得
以前はデータ通信のみの対応だったMVNOですが、近年は通話も可能なタイプも増加してきました。その時点で使用している電話番号をそのまま乗り換える『MNP(番号ポータビリティ)』です。
大手キャリアからMVNOに乗り換えるには、まず自身が利用しているキャリアのショップ窓口に行くか電話、あるいは公式サイトなどで転出の意思を伝えます。そしてMNP予約番号を受け取りましょう。
有効期限内にMVNOと契約
次に新しいMVNOと契約します。
MNP予約番号には通常15日の有効期限が設定されていることに注意してください。この期限を過ぎてしまうと、予約番号が利用できなくなるので注意しましょう。
無事に契約を終えると、SIMカードが配送されます。受け取ったSIMカードをスマホに挿し、初期設定をして完了です。
文/編集部
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










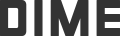 最新号
最新号






