インパクト投資とは、経済的なリターンを得るのと並行して、社会課題や環境課題を解決するために、行なう投資のことであり、2007年にロックフェラー財団が提言した用語である。
我々人類が、この地球で暮らし続けるために必要な目標を立てて、環境課題や貧困問題などを解決していこうというモチベーションが高まっている。その最たる例が持続可能な開発目標(SDGs)だ。国連が採択し、国内外の様々なところで目にする機会がある。
本記事で紹介する「インパクト投資」もその考え方の一担を担っているのだが、まだ認知度は高くない。このほど2022年10月25日に、金融庁が「インパクト投資等に関する検討会」を設置し、インパクト投資の拡大や、その投資先が行なう事業の拡大を目指して、有識者と議論をする取り組みを始めた。
今後、主要な投資テーマとして脚光を浴びる可能性を秘めているので、「インパクト投資」について、今のうちから詳しくなっておこう。
インパクト投資の定義:社会的・環境的な変化を測定するために新たな軸を持たせる
まずはインパクト投資の定義を理解しよう。
そもそもインパクト投資のインパクトとは、事業の結果で生じた社会的・環境的な変化や影響・効果のことを現す。
投資のほうは皆さんご存じの通り、リスクとリターンの2軸で考えながら、リスクを小さくし、リターンを得ていく取り組みの事である。
インパクト投資では、投資の結果、どのような課題を解決できたか。またその課題解決量はどのくらいか測定することで、投資活動に「インパクト」という新たな視点を持たせている。
つまり、インパクト投資は、リスク、リターン、インパクトの3つの軸で評価する投資だといえる。
2017年から2021年にかけて右肩上がりで投資残高が増え始めている。対2017年比で2021年は5倍となっている。国内では、2019年以降急激に残高を伸ばしている。
後段で詳述するが、インパクト投資では、投資対象に対してリターンを求めると共に、その投資対象が、社会問題や環境問題を解決できるか。解決するとしたらどの程度かを測定するという特長がある。
インパクト投資の定義に欠かせない4つの要素
インパクト投資では、上図の通り、4つの要素が備わっている必要がある。
社会や環境課題を解決する意図や、並行して財務的なリターンを追求する目的に加え、前掲載図にあるように、株などの多彩な資産での投資ができることが要素に含まれているが、特に「社会的インパクト評価」ができないとインパクト投資とは言えない。
社会的インパクト評価は行わないが、環境問題などを解決するために行なう投資があるが、これはESG投資として区別されている。ESGはそれぞれ、環境(E)、社会(S)、ガバナンス(G)の頭文字である。
一見すると、経済的な効果と、社会課題や環境課題の解決は、相反しているようにも見える。
営業活動を行なう企業の視点では、社会課題や環境課題の解決は、コストとして捉えられがちだからであろう。
視点を広げでその企業の関係者(ステークホルダー)の視点に立つとどうだろう。例えば、海外で教育のサービスを手掛ける企業の場合、そのサービスを利用する生徒数が増えれば、企業の利益が増えるし、教育を受けた生徒の識字率が上がるという効果も見出せる。
そもそも企業は、何かしらの社会課題を解決するために価値を生み出して利益を上げているという見方もできるが、とりわけ、SDGs(持続可能な開発目標)に紐づいた環境や社会問題の解決ができる企業や団体への投資でかつ、どのくらいのインパクトがあったのか。測定できる投資が「インパクト投資」として定義付けられているというわけだ。
インパクト投資の事例:国内でもすでに様々なファンド設立や投資活動が行われている
インパクト投資の事例を2つ紹介する。
●はたらくFUND
 引用元:はたらくFUND
引用元:はたらくFUND
1つ目ははたらくFUNDという投資ファンドで、新生銀行グループと社会変革推進財団が出資し、子育てや介護、新しい働き方といった、働き方に関連する事業への投資を行なっている。
保育士不足や、次世代の人材育成といった課題解決を目指す企業に投資し、投資リターンとインパクトの両方を得るべくその活動を継続している。
●三井住友信託銀行「住友ゴム向け ポジティブインパクトファイナンス」
低炭素社会の実現に向けた環境にやさしいタイヤ作りを行なうなどでSDGsを意識した経営を行なう住友ゴム社に対して、三井住友信託銀行が締結した融資契約(参考プレスリリース)である。インパクトを意識した金融活動が着実に進められている点を知っておいて欲しい。
インパクト投資の拡大には認知も事例もまだまだ不足している
 引用元:GSG国内諮問委員会
引用元:GSG国内諮問委員会
インパクト投資の考え方の浸透は始まったばかりで、上図のように、認知や事例が少ないのが、岸田政権が掲げている「新しい資本主義」の中でもトピックスとして取り上げられている。瞬間的なバズワードで終わるというよりは、投資のひとつのカテゴリーとしての地位を確立していくと見られる。
社会への浸透が広まるにつれ「インパクトウォッシュ」という見せかけの社会や環境課題解決を行なう事例も出てくると言われている。正しくインパクトが評価できるのか。適切にインパクト投資を行なうためのインパクト測定・マネジメント(IMM)が行えるのかがカギとなりそうだ。
参考:インパクト測定・マネジメントに係る指針(GSG国内諮問委員会)
取材・文/久我吉史
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE










 インパクト投資の市場規模
インパクト投資の市場規模



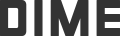 最新号
最新号






