コロナ禍を機に、一気に加速した「DX」だが、行きつく先にはどんな未来が待っているのか。2020年の都知事選にも立候補した小説家、沢しおんが2040年のTOKYOを舞台にIT技術の行く末と、テクノロジーによる社会・政治の変容を描く。
※本連載は雑誌「DIME」で掲載しているDX小説です。
【これまでのあらすじ】
二十年のうちにデジタル化が浸透した二〇四〇年の東京。都庁で近々役割を終える「デジタル推進課」の葦原(あしはら)は、量子ネットワークから消えた住民データの調査を進め、刑事の常田(ときた)と水方(みなかた)は橘広海(たちばなひろみ)の行方を追っていたが、その妹の橘樹花(じゅか)は ──。
憂鬱とアンドロイド教師
──大切な人は、私の前からみんな消えていく。
樹花は放課後、校舎の窓から中庭の池を見下ろした。校門から続く石畳の先に鎮座している池は、ちょっとした名所だ。円形から扇をくり抜いた形をしていて、今の季節は蓮の葉が広がっている。あと一か月もすれば花がきれいに咲くのだろう。
昨日の〝お出かけ〟で櫛田(くしだ)ヒメナとはとても気が合った。ランチもショッピングも楽しかった。あの人はきっと、儚さを気丈さで隠している、私にはわかる。
でも、踏み込んだらきっとまた失ってしまう──。
「樹花! また考え事してる。お兄さんのこと心配なんだよね?」
クラスメイトの千代子(ちよこ)だ。前と変わらず身体を寄せ、視線の先を一緒に見てくれる。
「違うよ。なんとなく、色々」
樹花は適当にごまかした。〝元カノ〟には、誰かを思っていたことなど勘づかれたくない。
「警察はちゃんと捜してくれてるの? 動画で拡散したらいいのに」
「この顔晒して? それに嘘ついて近づいてくるヤツいるし、そういうの面倒」
「あー……。たしかに危険だね」
千代子は顔をしかめるように片目をぎゅっとつぶった。ばつが悪い時の彼女の癖だ。
樹花と千代子は春休みが始まるまで付き合っていた。ずっと同じ教室で過ごしたクラスメイトは、二人がくっついたことも別れたことも誰一人気づかない。樹花にはそれが少し悔しかった。
春休みの間、別れのショックでずっと塞ぎこんでいた。
新学期からは、少しくらいよそよそしくしたほうがいいかと考えたが、始業式の日に〝彼氏〟と腕を組んで歩く千代子の姿を見てどうでもよくなった。もっと早く紹介してくれれば、開き直って春休みを過ごせたのに。
ようやく別れを吹っ切ったと思ったら、兄が失踪した。幼いころにいなくなった親と同じ、突然にだ。
「昨日さ、住んでるとこで選挙があったんだよ。クギカイギインセンキョ」
千代子の話題の変え方は極端で、脈絡がない。これも彼女の癖だ。
「初投票じゃん」
「そうそう。親が日本レガシー党の人に入れろってうるさくてさ、押し付けるなんてほんと人権侵害。ま、私の名前に国歌から二文字もってきたくらいだから」
千代子は溜め息をついた。樹花にとっては澄んだ音に〝チョコ〟ってあだ名も可愛いし、いい名前だなと思っている。
「想いを込めてつけてくれたってことでしょ。投票って、スマホでやったの?」
「親の前ではね、一度スマホで入れた。そんで昨日の帰りは一人だったから、投票所に寄って紙で入れてきた」
「めんどくさ」
「投票日までならスマホで入れた票はキャンセルできるって、彼が教えてくれて」
このところの千代子は、樹花の知らない知識を彼氏から仕入れてきて教えてくれる。
「チョコの彼は物知りな人でいいね」
「樹花は来月だよね、誕生日。そしたら投票に行けんじゃん」
「まだ覚えてたんだ」
「忘れないでしょ、親友の誕生日なんだから」
千代子の頭の中ではすでに〝親友〟のラベルが貼られているようだった。
樹花が再び池へと目を向けると、教師の周りをたくさんの生徒が取り囲んでいた。顔はなんとなく見覚えがあるが、名前が出てこない。
「あの人? 一年生の所に来た実習生。アンドロイドらしいよ」
「アンドロイド? アメノナツキみたいな?」
「そう。去年情報の授業にアバターの先生いたじゃん」
千代子によると、どうやら教育用AIにアバターをつけてリモート授業をしたのが去年で、今年はそれにアンドロイドの身体を与えて教育実習生にしたようだ。以前デジタルツインのボットについて樹花に教えたのも千代子で、彼女はITにやたらと詳しい。
樹花は千代子と近くまで行ってみることにした。
「去年と同じAIなら、私たちのこと覚えてるかな。一対一のリモートとかだるくてずっとすっぴんだったから、顔が一致しないかもしれないけど」
千代子は「AIなんだし、わかるでしょ」と笑った。
「じゃあチョコの彼氏はすっぴんでも千代子だってわかるの?」
「……驚かれたことはある」
化粧をしていない顔を千代子は彼氏に見せたことがあるんだ、と樹花は思った。
階段を降り中庭へ出ると、さっき上で見ていた時より生徒の数は増えていた。アンドロイド教師と一緒に写真を撮ったり、質問攻めにしたりしている。
「アバターだと生徒が何人いても同時に授業できるのに、身体があるせいで一度に相手できないの、技術の無駄じゃない?」
千代子の素朴な疑問に樹花もその通りだと思い、アンドロイドに近づいた。
「先生、情報の授業を受けもってくれたアバターだよね。顔も同じだし。どうしてアンドロイドになったの?」
樹花が気軽に声をかけると、その教師は目を合わせて微笑んだ。
あらかじめ千代子から聞いていなかったら、この教師がアンドロイドということには気づけそうもない。樹花にはこの教師が人間そのものに見えた。
「橘樹花さん、一年ぶりですね。勉強頑張っていますか。私が身体を得たのは東京都と民間企業が共同で行なっている実証事業のためです」
覚えていてくれた。けれどその回答は樹花には少々わかりにくかった。
「実証って何、実験ってこと? 実習じゃないの」
「アンドロイドは自然人ではないので教育実習生にはなれません。講義動画やアバター、それに理科室の人体模型と同様に教材として扱われます」
「人体模型と一緒かぁ。こんなに人間みたいなのに」
樹花は以前葦原が言っていた、精巧な人型アンドロイドを導入できる職種には制限があるという言葉を思い出した。
「橘さん。お兄さん、見つかるといいですね」
急に教師がプライベートなことを言ってきたので、樹花は息を呑んだ。千代子に心配されるのとは違う。あまり話したことのない他人に土足で立ち入られた、そんな気がした。
「それは私の個人情報ですけど、何で知ってるんですか」
樹花にさっきまでの気軽さはなくなっていた。
「私は思考回路の一部に東京都のAI、ヌーメトロンを使用していて、ワイヤレスで常時接続されています。橘さんの学業に関する情報だけでなく、ヌーメトロンが知っていることはすなわち私も知っているということになります」
「ヌーメトロンって、何? 私の何を知られているっていうんですか」
樹花がアンドロイドを問い詰めた時、校舎から別の教師が慌てて駆けてきた。
「放課後にあまり長い時間動かすなって言われてたんだ。今日はここまでな!」
生徒たちは名残惜しそうにしながら散っていく。「三年生の橘だったよな。今アンドロイドから言われたこと、気にすんな。まだ会話がうまくできないんだ、機械だからな」
アンドロイドを連れに来た教師はずっとモニタリングしていたらしい。
あのアンドロイド教師は会話がうまくできていないのではない。あまりにも自然で、そして知り過ぎている。
教師たちが校舎へ戻っていったのを見届けて、樹花は千代子に言った。
「あのアンドロイド、怪しい。AIがあんなこと言う?」
それから樹花は、ヌーメトロンについて葦原に聞いてみようと思い、スマホを取り出した。
(続く)
※この物語およびこの解説はフィクションです。
【用語・設定解説】
スマホで投票:2040年では一部でスマホやPA(パーソナル・アシスタント)端末からの投票が始まっている。懸念が多かった遠隔電子投票において、秘密投票が守られ、投票が強要されることのないようなフローが採択された結果、当日までならキャンセルでき、なおかつ投票用紙での投票が優先されることになった。
アンドロイド教師:ロボットやドローンへの抵抗感をなくし人間との業務分担を円滑にするために、芸能分野で発展した人型の「アイ・ドロイド」を応用。対人コミュニケーションを必要とする現場へアンドロイドを配備する実証事業が各地で行なわれている。
沢しおん(Sion Sawa)
本名:澤 紫臣 作家、IT関連企業役員。現在は自治体でDX戦略の顧問も務めている。2020年東京都知事選にて9位(2万738票)で落選。
※本記事は、雑誌「DIME」で連載中の小説「TOKYO 2040」を転載したものです。
過去の連載記事一覧はコチラ
この小説の背景、DXのあるべき姿を読み解くコラムを@DIMEで配信中!
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE











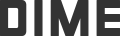 最新号
最新号






