TOKYO2040 Side B 第19回『メディアからコミュニティマネジメントへの「再DX」を意識する』
※こちらの原稿は雑誌DIMEで連載中の小説「TOKYO 2040」と連動したコラムになります。是非合わせてご覧ください。
これからのSNSはどうなる?
Twitter社がイーロン・マスク氏に買収されたことが話題になっています。ゴシップ的に大量解雇や運用方針の改革に注目が集まり、これまでの投稿に対するランク付けやキュレーションが偏っていたのではないかという指摘も相次いでいます。
今回はこれまでのSNSがどうメディア化したかをWeb1.0から振り返りつつ、それに合わせてビジネスユーザーにとってのメディアの用い方が大きく変わり、「再DX」が起こるという話をしたいと思います。
Web1.0時代は本当に一方通行だった?
TwitterをはじめとしたSNSはWeb2.0を象徴するサービスですが、この15年でメディアを兼ね備えるプラットフォームへと大きく変容し、マネタイズ手法も変わりました。
よくWeb2.0は双方向性の時代と言われることが多いですが、それだけではないと考えています。
Web1.0の時代は「HTMLを書ける表現者兼管理者」がコンシューマーの利用者に多くいました。発信に求められる技能のハードルが高かったとはいえ、ブログやSNSという言葉やクラウドサービスが無くても、懐かしの「ホームページ」に実装されたBBS・掲示板・Webリング・アクセスカウンターなども含めるとコミュニケーションの機能は実装されていましたし、個人レベルでの発信だけでなく、それらを繋いだコミュニティすなわちソーシャルネットワークもオン/オフを問わず成立していました。
このため、Web1.0が必ずしも「大手メディアやアカデミアが発信したページを一方的に享受するだけの時代」だったわけではないと考えるのです。
おそらく一方通行のイメージがあるのは、国内におけるiモードの大成功によって、情報を受け取る使い方への印象が大きいからかもしれません。
Web2.0で何が飛躍したのか
では、Web2.0時代に何が大きく変わったのでしょうか。ハードウェアやインフラとしてはスマホや4G・LTE通信の浸透が挙げられ、ソフトウェアではパッケージ(ダウンロード/インストール)かサーバークライアント型かクラウドのWebサービスかを問わず「アプリ」と呼ばれるようになりました。成り立ちや構造で区別をつけなくなったと言えます。
これらは利用者の裾野が広がって、Webがページ上の読み物からサービスインフラとして一般化したことの現れでもあります。
その上に乗る仕組みとしては、「アドネットワーク(広告配信の仕組み)」と「レコメンデーション(おすすめする仕組み)」が広範に用いられるようになったことが、Web1.0とWeb2.0の時代で大きく異なる点だと考えています。古くはブラウジングにおける「クッキー論争」を覚えている人もいらっしゃるかと思いますが、この15年ほどWebサービスは「視聴読者を特定して好みを絞り込んでいく」ことを熱心にやってきたのです。
SNSメディアの先鋭化
この流れは冒頭のTwitterの話にも結びつきます。「ホーム」画面にフォロー/フォロワー関係なく、サービス側がおすすめと思われる投稿や広告を差し挟んでくる。FacebookやInstagramもそうなっていますし、TikTokだとそもそも「おすすめ」がメインストリームです。
本来SNSはメディアではありませんでしたが、人が人を呼んで母数が大きくなるとともに発信力や影響力の有無が可視化されます。それに加えて受容する側の趣味嗜好も統計に表れるようになり、先述したレコメンデーションによっておすすめされ、最適な広告がアドネットワークによって配信されます。
サービス側から見て、利用者本人が自覚している「見たいもの」はあまり信用されず、「見たかったでしょ?」と統計的エビデンスをもって勧められるもののほうが信用されている状況と言えます。
基本無料のサービスにとって、マネタイズが広告だった故にこのように先鋭化したわけですが、利用者からするとノイズが限界まで混じってしまっている状況にも見えます。
コミュニティの再DXから起こる変容とは?
こういったSNSのメディア化、広告最適化という背景がありつつ、ビジネスユーザー全てがこの比較的新しいメディアを使いこなせているかというと、難しいと言わざるを得ません。
例えば雑誌やテレビといったマスメディアに広告を打つ場合、媒体資料として必ずターゲット層が明示されます。元来のメディアであるため、テーマへの関心度合いもさることながら、老若男女でどのような視聴読者が分布しているかが重要だからです。
ですが、メディア化しているとはいえWeb2.0時代の荒波に揉まれた進化をしているのがSNSですから、一筋縄ではいきません。
いまだに「若者へリーチしたいのでTikTokを使いたい」「メッセージアプリのアカウントを運用したいが若い人はインスタのDMでしか遣り取りしていないのではないか」という切り口でSNS利用の相談を受けることがあります。
SNSアカウントの活用は無料でオウンドメディアが持てる点にビジネス的な魅力がありますが、結局、各プラットフォーム内での集客・フォロワー増加に関する壁が立ちはだかります。フォロワーを増やすために別の広告を打つところまで行くと本末転倒でさえありますね。
15年で進化し、常に新しい傾向が表れているのにも関わらず、いまだに「多くの人が集まっているのならそこに何かを放り込めば効果が出るだろう」というのでは短絡的ですし、ビジネスユーザーにとってはその方針で投じたコストは無駄になってしまうことでしょう。
さらに、冒頭に書いたTwitter社の事例のように、プラットフォーム企業の経営事情によって投稿した内容が意図した状態でいつまでも保たれるかどうかという点で疑問が生じることも十分に考えられます。いつでもプラットフォーマーの方針転換や、掲載アルゴリズムの変更が起こるとも限らない。
ここで、これらSNSを中心としたコミュニティの再DXについて考えます。すでにデジタル上で変容し続けたものを相手にするので「再」というわけです。何が変容するのか。それはビジネスユーザーのメディアへの接し方、利用者の扱い方です。
価値への寄付、そしてコミュニティマネジメント
数年前にオンラインサロンが話題となりました。同時にサブスクやクラウドファンディングも浸透し、消費者がお金を払うべき価値の姿が多様化しました。15年前では事業化が難しかったユーザーからの投げ銭も、YouTubeのスーパーチャットを始めとした動画配信サイトでのギフト機能で一般化してしまっていますし、このコラムでも何度か触れているNFTやDAOトークンも含めてそれらの購入を「価値への寄付」と考えると解釈しやすいです。
マネタイズの背景が変わっている。これはWeb2.0で起こってきたことの延長ですね。では、かつて「おすすめ」が「広告収入」と深く結びついてきたように、今度の「価値への寄付」が何と結びついているかを考えると良いということになります。
オンラインサロンとして名を馳せたネット上のコミュニティサービスは細かく機能が分割されてメンバーシップと名を変え、多くのWebサービスに取り入れられています。それに応じてサブスクにランクが設けられ、オプションで追加料金が発生するなど「同じブランドのサービスなのに利用者それぞれによって払う金額が変わる」現象が起こっています。クラウドファンディングによってあらかじめ付加価値を利用者が予約しておくというのもよく見られます。
マネタイズの要求に応じて、すでにサービス側が大きく変容しているわけです。当然、利用者からの見え方も変わっています。
Twitterの例にならうと、レコメンド広告主体だったのが、サブスクの「Twitter Blue」を始めとした有料メニューの違いによって、利用者それぞれに合った違う体験をするというイメージです。
ビジネスユーザーがこれらSNSの流れをうまく使い、メディアとして利用するにあたっては、SNS上の活動や投入するコンテンツにおいて、いかに価値の設計を行い、高客単価層から無料ユーザーまでを細分化してコミュニティマネジメントするかが肝要ということになります。
案外難しそうですが、本誌12月号で特集された「VTuber」は、YouTubeのメンバーシップを用いてファンクラブ的に幅広く顧客(視聴者、ファン)とのリレーションシップを築いている人も多く、ヘイトや炎上のリスクマネジメントをしている好例と言えます。だからこそ、最先端のITビジネスであり、上場企業も出現しているわけですね。
刻一刻と変化しているものについて、しがみつくやり方だけでなく、どんな変容が起こっているのかを整理すること、背景にある流れを理解することで、こちら側の変容に繋げることが重要と言えるでしょう。
本誌連載では…
本誌連載の小説『TOKYO2040』の最新19話では、ドキュメント、メタバース、そしてリアルという三種類の「プラットフォーム」を相手に、主人公や刑事たちが失踪事件の真実にそれぞれのアプローチで近づこうとしています。是非御覧ください。
文/沢しおん
作家、IT関連企業役員。現在は自治体でDX戦略の顧問も務めている。2020年東京都知事選に無所属新人として一人で挑み、9位(20,738票)で落選。
このコラムの内容に関連して雑誌DIME誌面で新作小説を展開。20年後、DXが行き渡った首都圏を舞台に、それでもデジタルに振り切れない人々の思いと人生が交錯します。
これまでの記事はコチラ
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE












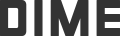 最新号
最新号






