冬のアミューズメント施設の目玉はナイトウォーク
この冬、さまざまな施設やエリアで人気が高まっている「ナイトウォーク」をご存じだろうか。
「富士すばるランド」(山梨県富士河口湖町)では、アミューズがプロデュースする体験型アドベンチャー「ナイトウォーク~クライの森と6つの星〜」を2022年7月30日~10月30日の期間限定で開催。
閉園後の富士すばるランドを、不思議なカメラを持って冒険の旅に出て、見えない敵をカメラで写してミッションをクリアする、という設定。リアルと仮想を行き来し、感情をゆさぶる新感覚の体験型アドベンチャーだ。
ムーミンの物語を追体験できると人気の「ムーミンバレーパーク」(埼玉県飯能市)では、「ムーミン谷のナイトウォーク~イルモリノオト~」を2022年10月22日から2023年1月9日の期間、開催する。宮沢湖の外周を舞台とした光の演出と、現実世界に仮想世界の音が混ざり合うソニーによる新感覚の音響体験Sound AR™を組み合わせ、散策のペースに合わせて耳元から流れるストーリーを聞きながら全長約1.8㎞の湖畔の道を進むアトラクション。まるでムーミンの物語の中を冒険しているような感覚を体験できるという。
「ハウステンボス」(長崎県佐世保市)では11月4日まで「花の街のハロウィーン〜秋の大収穫祭〜」を開催。約2500個ものかぼちゃランタンに包まれながらハロウィーンをイメージしたイルミネーションショーを散策できる「ハロウィーンナイトウォーク」が毎年人気だ。
その土地の魅力を引き出す幻想的なナイトウォークイベント
また、ナイトウォークをキーコンテンツとした観光スポットをクリエイティブカンパニーと地方自治体が協業で創出し、成功させている例も。2022年9月30日から2023年2月26日まで、佐賀城公園・県庁展望ホール・ARKS(佐賀県佐賀市内)で開催されている「夜歩きアート県庁NAKED GARDEN SAGA」もそのひとつ。メタバース・NFTを活用したXR体験型アート &空間演出などを得意とする「NAKED, INC」と佐賀県が2016年から実施している「アート県庁プロジェクト」の目玉で、これまでに県内外から約21万人が来場している。
同イベントでは、コロナ禍でも安心安全に観光を楽しむ取り組みとして、光の輪でソーシャルディスタンスを保ちつつ、自身も光の演出に加わることができる参加型アート作品「NAKEDディスタンス提灯®」の無料貸し出しを実施している。お祭り診断サイトでおすすめのお祭りを診断し、診断結果に基づいたカラフルな提灯を貸出す。
2021年3月19日から4月11日に世界遺産・元離宮二条城で開催された体感型アート展「NAKED FLOWERS 2021 −桜− 世界遺産・二条城」では、「NAKEDディスタンス提灯®」桜バージョンを手に回遊すると、清流園エリアでは本物の桜のライトアップと呼応するインタラクティブ演出も登場
観光都市として揺るぎない地位を誇る京都だが、京都をひとつの庭と見立て、リアル×メタバースで楽しむ次世代型アートプロジェクト「NAKED GARDEN ONE KYOTO supported by 三菱UFJ銀行」(2022年12月25日まで)も注目だ。リアルとバーチャルが融合した様々な体験を通じて、より多くの人々に京都の文化発信するのが狙いで、京都市、宇治市、滋賀県大津市に加え、三菱UFJ銀行、サイバーエージェントなどをプロジェクトサポートのパートナー企業として迎え、現在、18箇所の参画箇所を発表している。以下はその一部。
宮津市で行われる関連イベント「宮津・天橋立ナイトウォーク」(10月14日~11月13日)では、日本三景の一つである天橋立(あまのはしだて)などがインタラクティブアートやライトアップで演出された街並みのナイトウォークを楽しめる。
京都市の中でも人気のエリアである貴船神社を有する貴船エリア。関連イベント「京の奥座敷・貴船もみじ灯篭」(11月5日~11月27日)で「ディスタンス提灯®」を持ちながら、幻想的で神々しいライトアップ空間を体感できる。
関連イベント「京丹後市ナイトウォーク」(11月18日~12月18日)では、京丹後市の複数エリアを「灯り」でつなぐ参加型アートを実施。京丹後の自然とネイキッドのアートが融合する空間を体感できる。
ナイトウォークの本質は、光のない闇を歩くことにある
光と闇が描くアートを全身で体感するのもナイトウォークの楽しみのひとつ。だが、「闇歩き協会」を主宰する闇歩きガイドで、『「闇学」入門』(集英社新書)を始め “闇”に関する著作が多い専門家の中野純氏はナイトウォークの本質を、「光のない闇を歩くことにある」という。
 中野純(なかの・じゅん)氏。体験作家、闇歩きガイド。一橋大学社会学部卒。主な著書に『「闇学」入門』(集英社新書)、『闇と暮らす。』(誠文堂新光社)、『庶民に愛された地獄信仰の謎』(講談社+α新書)、『闇を歩く』(光文社 知恵の森文庫)、『月で遊ぶ』(アスペクト) 『闇で味わう日本文学 失われた闇と月を求めて』(笠間書院)など。東京造形大学非常勤講師
中野純(なかの・じゅん)氏。体験作家、闇歩きガイド。一橋大学社会学部卒。主な著書に『「闇学」入門』(集英社新書)、『闇と暮らす。』(誠文堂新光社)、『庶民に愛された地獄信仰の謎』(講談社+α新書)、『闇を歩く』(光文社 知恵の森文庫)、『月で遊ぶ』(アスペクト) 『闇で味わう日本文学 失われた闇と月を求めて』(笠間書院)など。東京造形大学非常勤講師
元々山登りが好きだった中野氏が、初めて「闇歩き」を体験したのは1994年の初夏のこと。高尾駅で終電を逃し、始発までの暇つぶしに、気軽に登れる高さの東高尾の山に懐中電灯を持って入ってみたという。その時に、昼間の森とは別世界の幻想的なモノトーンの森が現れたことに興奮し、毎夜現れるこうした別世界を全く無視してきたことに強い違和感を覚えた。
そこから終電に乗って深夜の山へ行くミッドナイトハイクを楽しむようになり、天然の光と闇のドラマにますます魂を奪われていく。ついには闇についての研究や考察を著わした本を何冊も上梓するように。2002年からは有料の闇歩きツアーを始め、大学の授業やカルチャーセンターなどで闇についての講座を開くようになり、現在では仕事の8割が暗闇関連だという。
ナイトウォークは、日本伝統のレジャーだった!
「闇について調べていくと、日本の文化のほとんどすべてが闇によって育まれ、日本人の感性が闇から湧き出してきたこと、それが世界的に見て特異なことだとわかってきた。日本には昔から蛍狩り、虫聴きなど闇に親しむ文化があった。そして山に夜中に登り、ご来光を拝んで下山する闇の登山を、最高のレジャーにしていた」(中野氏)。
つまりナイトウォークは決して新しいブームではなく、日本の伝統的なレジャーなのだという。そもそも室町時代以前には山伏が、修業の一環として暗闇での山歩きを行っていた。やがて江戸時代になるとその山伏の中の一部が山岳ガイドの役割を果たすようになり、夜間の長時間に渡る山歩き=ナイトハイクが、庶民が楽しむレジャーとしてブームになっていく。
志賀直哉の「暗夜行路」も、標高1711mの伯耆大山(ほうきだいせん)を志賀直哉自身が無灯火のナイトハイクをした実体験をもとに書かれている。自然の闇の中に自分が溶け込んでいくような、陶酔的なナイトハイク体験を通して、主人公の謙作が人生の苦悩から解き放たれるクライマックスは、日本近代文学史上あまりにも有名だ。
また宮沢賢治も生徒を引率して岩手山にナイトハイクしているし、本屋大賞を受賞し、映画にもなった恩田陸の小説『夜のピクニック』のモデルとなった茨城県立水戸第一高校の「歩く会」も、夜がメイン。各地の高校や大学でもずばり「ナイトハイク」という、夜をクライマックスとする強歩大会の伝統行事が多い。
ナイトウォークの魅力①…生まれ変わったような感覚を体験できる
日本では古くから、山の上は死後の世界だと考えられてきた(山中他界観)。だから今でも山伏は山に入る時に、死に装束を着て登る。山に登って下山することで生まれ変わりの疑似体験をすることを、民俗学者の五来重(ごらいしげる)は、「疑似再生」と呼んだ。
そんな生まれ変わるための山伏のハードな修業を1日で簡易体験できるのがナイトハイクだ。中野氏は、数時間以上にわたるナイトウォークを「ナイトハイク」と定義しており、必ずしも登山に限定していないが、ある程度の標高の山に登るとなると、どうしても真夜中も歩き続けることになる。
「右も左もわからないほどの深い闇にたっぷり包まれて歩き、その後に山頂で日の出を見ると、ご来光はとてつもない爆発的な輝きに見えるし、昨日とはまるで違うまっさらな世界が始まるような、生まれ変わったような気持ちになる。生まれることとは、胎内の闇から胎外の光の世界に行くこと。再生のための演出としてご来光が効果的に使われたのだろう」(中野氏)。
中野氏も、ミッドナイクハイクの後に妙にすっきりし、家に帰って寝た後も気分のよさが続くと語る。ナイトウォークツアーの参加者からも「ツアー後、体調がいい」という声をよく聞くという。昼夜の明るさのギャップがほとんど無い生活を続けていると、体内時計が狂ってしまい、1日中ボーっと過ごしてしまいがちになる。「闇と光のドラマを失った現代人ののっぺりとした単調な生活は、知らぬ間にとんでもなく強いストレスを与え続けているのでは」と中野氏は危惧する。それを効果的にリセットできるのが、ナイトハイクなのだ。
ナイトウォークの魅力②…五感が研ぎ澄まされ、「ものを見る」力が養われる
深い闇の中では五感が鋭くなる。聴覚や嗅覚が敏感になり、わずかな音や匂いを鋭敏に感じるのはもちろん、視覚も劇的に変化。暗闇の中では超高感度になり、「夜目」で物を観ることができるようになる。また、明るいところでは真ん前の中心にピントを合わせて物を見るが、暗い闇に順応すると逆に周辺のもののほうが見えやすくなる。
この状態は宮本武蔵の武道書『五輪書(ごりんのしょ)』に書かれている、「観の目」(全体をいっぺんにとらえる目)にも通じる。敵の刀にピントを合わせず大きく広く全体を見ることを普段から心がけることが武道の上達のために大事だと、宮本武蔵は説いている。これは武術に限らず、球技や他のスポーツにも通じる。山伏たちが闇の山を駆けたり洞窟にこもったりして修業をしたのは、超能力者になるため。超能力をもたらすために必要なのが、暗闇だったのだ。
松井秀喜選手も、選手生活の中の一番の思い出として、長嶋監督に闇の中で素振りをさせられたことをあげている。長嶋監督はあえてスイングを見ずに、スイングの音を聴いていい音が出たら終わりにしたという。
デジタル機器など目の前のものばかり集中して見ていると、まわりが見えなくなる。それが常態化している現代人は五感がどんどん鈍化していて、自分が観ているデジタル機器の画面以外は「闇」と同じになっているともいえる。だからこそ、深い闇の中に身を置いて「五感でものを見る」心を養う必要があるのだ。
ナイトウォーク体験のすすめ①…イベントに参加
ここまで読んで、「ナイトウォークを体験してみたい」と思った人も多いだろう。だがナイトウォークには危険が伴うことも多いので、中野氏はツアーなどに参加することから始めるのをすすめている。「ナイトウォーク」で検索すると、宿泊者限定で60分ほどのナイトウォーク体験ができる「信貴山観光ホテル」などの宿泊施設がヒットする。
また和歌山県にある高野山の奥之院では、毎月20日の夜に「お逮夜(たいや)ナイトウォーク」が行われている。お逮夜ナイトウォークとは、弘法大師空海が入定(にゅうじょう)された旧暦の3月21日にちなんで、お大師様を偲びながら奥の院参道を御廟まで歩くイベント。参加料金は無料で予約の必要もなし、20日当日の夕方に一の橋案内所(和歌山県伊都郡高野町高野山555)まで集合すれば誰でも参加ができる。※詳しくは高野山HPで確認を。
中野氏も夜の山、里、街、海辺や洞窟などを、なるべくライトに頼らずに、闇を楽しみながら歩く「闇歩きツアー」を企画・案内している。

 中野氏が企画・案内している「闇歩きツアー」。超初心者向けの「イージーオーダー・ナイトウォーク」(2,000~2,500円※4月~10月限定)や、「オーダーメード闇歩きツアー」もある
中野氏が企画・案内している「闇歩きツアー」。超初心者向けの「イージーオーダー・ナイトウォーク」(2,000~2,500円※4月~10月限定)や、「オーダーメード闇歩きツアー」もある
ナイトウォーク体験のすすめ②…日本文学の中の「闇」を実体験してみる
中野氏の近著「闇で味わう日本文学 失われた闇と月を求めて」では、古典文学の中に保存された豊かな”闇”をピックアップしている。
中野氏のおすすめは、まず日本文学を通して闇を体験し、その闇の世界を現代生活の中で再現したり、その現場に行ってみたりしてからその文学を再読すること。つまり、作品が書かれた時代と現代を往復することで、その作品に描かれた闇を体験することができるのだ。
 「闇で味わう日本文学 失われた闇と月を求めて」(中野 純 (著), スケラッコ (イラスト)/笠間書院)。日本文学の中の豊かな”闇”を体験できるブックガイド
「闇で味わう日本文学 失われた闇と月を求めて」(中野 純 (著), スケラッコ (イラスト)/笠間書院)。日本文学の中の豊かな”闇”を体験できるブックガイド
あなたもこの冬、自分なりのやり方で「ナイトウォーク」に挑戦してみてはどうだろう。身近にあったのに気が付かなかった、もうひとつの世界の扉が開くかもしれない。
取材・文/桑原恵美子
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE
























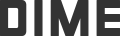 最新号
最新号






