
横浜市中区の海岸通りに、ひときわ目立つ建物がある。古代ギリシャ建築(コリント式)の16本の円柱がズラリ並ぶ、神殿を思わせるようなビルがそれである。
日本海運業の歴史が凝縮
竣工は1936(昭和11)年。日本を代表する海運会社、日本郵船の二代目横浜支店として長年使われており、2003(平成15)年には1階部分に同社の歴史資料館を入れ、「日本郵船歴史博物館」と改称して一般公開している。
博物館法でいうところの「博物館類似施設」にあたるため、日本郵船という一私企業の宣伝施設と思われがちだが、2017年には先の天皇皇后両陛下(現、上皇上皇后陛下)がご訪問されている。
戦前、同社の筆頭株主が宮内省だったご縁に加え、ここが日本の近代海運業の歴史を知ることのできる貴重な施設であることの証と言えよう。
始まりは岩崎彌太郎
日本郵船の歴史を辿ると、岩崎彌太郎が土佐藩から経営委託を受け、1870(明治3)年に設立した回漕会社、九十九商会(後の三菱商会)まで遡る。
政府の信頼を得て日本初の外国航路(横浜~上海)を開設し、日本の海運業を発展させていったが、三井系・関西財閥が設立した共同運輸との熾烈なダンピング合戦が勃発。共倒れの危機に陥り、1885(明治18)年、両社は合併し日本郵船会社が誕生した経緯がある。
参考までに、共同運輸は井上馨、品川弥二郎、そして渋沢栄一らが大きく関わっており、幕末から明治に至る政界・財界の熱い戦いを伺い知ることができる。
シンボルマークは「二引(にびき)の旗」。合併した郵便汽船三菱会社(当時の名称)と共同運輸の2社を象徴し、地球横断と社運発展の願いがこめられている。
超レアなビルダーズモデル
館内は時代の流れに沿い、世界情勢の解説と、当時活躍した船関連の展示が続く。中でもひときわ目を引くのが、かつて同社が所有していた船のビルダーズモデルだ。製作したのは、日本の船舶模型のパイオニア、籾山艦船模型製作所。1/48スケールの圧倒的迫力と、精巧な造りは、他を寄せ付けない。
それもそのはず、ビルダーズモデルは造船所が船を発注してくれた船会社に対してお祝いとして贈呈したものなので、本物の設計図を元に製作する。しかも、金属部分は板を曲げるのではなく、真鍮の棒からの削り出しで金メッキ。船体は檜で造り、周囲を漆塗りという、美術品クラスの出来栄え。同製作所はすでに廃業していることもあり、これらのビルダーズモデルはお宝の域に達している。
昭和の豪華客船たち
昭和初期に活躍した客船の資料も興味深い。この時代、正しくは貨物とお客さんを乗せる貨客船という位置付けになるものの、当時のフラッグシップだった浅間丸(サンフランシスコ航路)の豪華な造りは、太平洋の女王と呼ぶにふさわしかったことが伝わってくる。
一等の乗船料は家一軒建てられるほどだったというので、現代の豪華客船より贅沢なものと思っていいだろう。
戦争と船会社の関係
日本の海運業を知る上で、忘れてはならないのが戦争との関係だ。明治から昭和にかけ、戦争のたびに船会社は所有する船舶を軍事目的で供出してきた。とくに太平洋戦争では、日本郵船は合計185隻を失い、社員5312人の犠牲者が出てしまった。
終戦後に残った船はわずか37隻。そのうち1万トンを越えるのは、今も山下公園前に係留保存されている氷川丸ただ1隻のみだった。
マニアにはたまらない品が揃うミュージアムショップ
館内をひとまわりした後は、ミュージアムショップものぞいてみたい。ここでぜひ注目したいのは、1/1250から1/300サイズの氷川丸や、自動車専用船、コンテナ船、客船(飛鳥)など日本郵船で実際に活躍していた船の模型。
製作は船や航空機の精巧な模型で名をはせる小西製作所。お値段は3万円前後が主流。オリジナルのサーモステンレスボトルも人気だ。
館長代理の常設展示解説がおもしろい
最後にクイズです。以前、船の名前にはある法則がありました。それはどのようなことだったでしょう? 以下の例を参考にしてください。
客船:氷川、浅間、秩父、八幡、新田…
貨物:対馬、能登、讃岐、箱根、富山…
おわかりになりましたか?
なお、博物館では毎月第1・3土曜日と第2・4木曜日の14時~15時に、館長代理による常設展解説(各5名まで、要予約)を行っている。堅苦しい話だけでなく、船にまつわる楽しい話がたっぷり聞けて、上記クイズの答えもわかりますよ。
ぜひ一度、訪ねてみてください。
取材協力:日本郵船歴史博物館
取材・文/西内義雄
医療・保健ジャーナリスト。専門は病気の予防などの保健分野。東京大学医療政策人材養成講座/東京大学公共政策大学院医療政策・教育ユニット、医療政策実践コミュニティ修了生。高知県観光特使。飛行機マニアでもある。JGC&SFC会員
















 DIME MAGAZINE
DIME MAGAZINE

















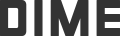 最新号
最新号






